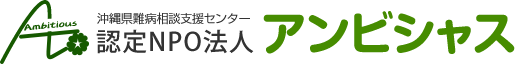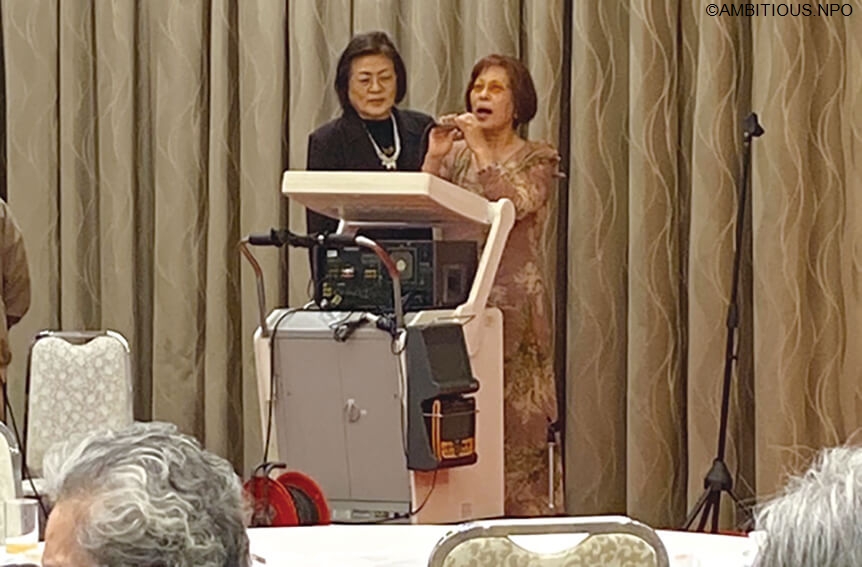- ホーム
- 難病情報
- 難病情報誌 アンビシャス
- 難病情報誌 アンビシャス 275号
難病情報誌 アンビシャス 275号
最終更新日:2025年04月01日

表紙は語る
アルビノとして生まれて ~ありのままに生きる~
小渡 里子(おど さとこ)さん
眼皮膚白皮症
病名のことを始めに紹介します。正式名称・登録名称は眼皮膚白皮症です。通称はアルビノで通ります。この病気は先天性の常染色体劣性遺伝で、スモールaの時だけ出てきます。黒色の色素、メラニン色素がもともと全く無いか少ないかなので、髪の毛や体毛、肌の色も白っぽく、色素量によって髪の色も瞳の色も様々です。私の色は名前がかっこよくて、これまでアメリカ人とか金髪とか、ハーフとか言われてきましたが、最近「あなたの髪の毛はプラチナブロンドよ」と、教えてくれた人がいました。今は、ヘアドネーションのために髪を伸ばしています。
アルビノは最近でこそ「綺麗な髪の毛ね」と言われるようになって、もはや幽霊と言われなくなったことは嬉しいですが、私の学齢期でもいじめがひどく、今もまだあると思います。私も就職差別をされたように、実習や就職先で髪を黒く染めるよう言われたりと、現在の日本でこんな感じですが、アフリカでは呪術目的でアルビノ狩りがされていて、命を取られてしまうこともあり、家の中に隠れているそうです。「綺麗だね」と言われて嬉しいけれど「綺麗だね」だけで済まない現実もあるんです。髪の色を見れば、だいたい色素量が分かるように、黒目の部分の色も色素量が少なければ少ないほど弱視で視力が低いんです。私は周りからかなり見えているように見られますが、実際の視力は0.01以下で、これは勘が働いている部分がすごく大きいです。何しろ生まれつきの視力なので、これが私の当たり前なんです。うーまくー※1でもあったので、子供の頃はあちこちアザだらけでした。木登りとかうんていとか、アルビノは紫外線と直射日光がダメなので、外遊びは夕方にやっていました。転ぶとかぶつかるとか気にしていたら何もできないという感じでした。
目に関して工夫というか、助けられているのは「ルーペ」です。ルーペは“補装具※2の対象”に無く自己負担ですが“弱視眼鏡(ルーペ眼鏡)”は申請できます。私の場合編み物をするので、両手があくのが良いですね。他には“単眼鏡”と言って、双眼鏡の単眼のもの。トイレやお店の看板が見えないので、首から下げて移動するときに使っていました。私が学生の頃は“単眼鏡”を知らなかったので“双眼鏡”で黒板を見ながら板書していましたよ。ただ最近はスマホがすごいですね。スマホのカメラモードは拡大して見えるので便利で手放せません。
小学校入学の時の話です。「盲学校へどうぞ」という案内が来たそうですが「病気のことを説明しますから、できるところまで普通校でお願いします」という母の申し出で、大学まで普通校に行きました。学年が変わるたびに母は、視力や日焼けのことなど担任の先生に説明してくれました。授業は耳で聞いて、録音しても聞いて、友達のノートを写す方法で、三回同じことを聞いていたので、すごく勉強しなくても頭に入っていました。授業ごとに毎回ノートを貸してくれた友達には本当に感謝です。
大学進学する時は、私は保育士さんや看護師さんになりたいと思っていました。でもそれは視力的に無理で。ただ、子供が好きだったので高校教師になろうと思い、県外の教育大学に行きました。しかし四年生になり、いざ教員採用試験の申し込みをしようとすると「障害者は受験できない」と言われてしまいました。その時は障害者差別禁止法はまだそこでは導入されていなかったのです。沖縄では既に障害を持った人も先生になっていたんですけどね。でも、当時学生だった私は良く分かっておらず、今はその時のことを問い合せても答えてくれませんが、いわゆる欠格条項だったというのは、ここ7、8年で分かったことです。
乗り越えきれない、どうにもできない社会の壁にぶち当たって、私はうつ病になりました。そのあたりから社会の壁に敏感に反応するようになり、就職差別もあって、正式に働いたことは二回しかありません。履歴書を出しても、いつまで経っても返事がなく、問い合わせるといつも「もう決まりましたから」と言われていました。でも今は、大学生活もこれらの経験も、すべて良い経験になったし、人生の中で不必要なことは一切無いのだと思っています。
私は今、目標があって“来ることに何の資格も条件も要らない、居たいときに誰もが居られる場所としての、地域に開かれた教会”を作るため、牧師になるための神学校へ向けて体調調整中です。毎週教会でピアノを弾き、最近はうるま市の教会で開かれるコンサートなどでウクレレの弾き語りもしています。
アルビノは、ヘルマンスキー・パドラック症候群(HPS)という難病を併せもつ場合があり、指定難病に入っていますが、難病登録をしていない仲間もたくさんいます。しかし、アルビノを研究する第一人者のお医者さんがいないので、第一人者に出てきてほしい思いを込めて、私は難病登録をすることにしました。アルビノのメラニン色素については、漫画のブラックジャックの中で「メラニン色素注入」とか出てきますが、そんなことは今の科学ではできないので、HPSの研究が進んでもらえたらいいなと思っています。
5月号では、人生の転機となった教会で知った“必要のない人間は誰もいない”ということや、私に何ができるのかについて語ります。
(次号に続く)
※1 わんぱく
※2 申請は各市町村窓口へ
語者プロフィール
小渡 里子(おど さとこ)さん
1974年 那覇市出身
【家族】くまお、ツリーちゃん
【好きな音楽】クラシック(ショパン)、讚美歌、ゴスペルソング
【最近の楽しみ、今年の目標】おにぎりプロジェクト考案中
※編み物で作ったおにぎりやえび天の飾りを販売して、材料費を引いた全額を、子ども食堂などへ寄付する、というプロジェクトを計画していて、寄付先は探し中です。
2025年2月の報告あれこれ
RDD2025㏌沖縄の報告
2月27日2時より「RDD2025 ㏌沖縄」を沖縄県立博物館・美術館講座室と八重山・宮古会場とZoom参加の方をオンラインで結び開催しました。
那覇主会場11名、八重山会場8名、宮古会場2名、Zoomによる参加10名、合計31名様にご参加いただき、難病患者ご本人、ご家族、医療福祉等の関係者、各行政関係者からご参加をいただくことができ、それぞれの立場に立ったご意見を催しの中ではいただくことができました。
催しの内容は、RDD 2024より繋がりました参加者の方々と共に、12回にわたり進めて参りました「難病と診断されたとき」に役立つしおりの経過報告を柱に、関わりを持つことの多い「医療者と良い関係をつくるには」、「どうしたら医療者に伝わるか」というテーマでグループワークをおこない、発表する時間を持ちました。
このなかでは、医療者に対して聞きたいことを予めメモや文書にまとめて準備しておくといった方法論的な意見や、医療者、患者という立場としての隔たりを持たず、対等な人として質問をするといった思惟的な意見など様々な考えが各グループから発表されました。
このようなご意見は、実体験としての生の声であり、経験した人でないと表現できない内容が含まれています。「しおり」はこうした当事者、家族でないと感じること、表現することが難しい内容を含んだ製作となっています。
今回のRDDは、これまでの経過の報告と、グループワークから出された貴重な意見は、「しおり」として記録に残し、難病と診断されたときに役立てていただけるよう、まずはデジタルしおりの公開を目指します。
この「しおり」が、まだ出会えていない難病に関わる全ての方の助けになるよう、2年目も制作活動に取り組んでいきたいと考えています。
ご興味のある方、是非一緒に「難病と診断されたとき」に役立つしおりを一緒に作成しましょう。
難病医療相談会(膠原病系疾患)
2月1日に新健幸クリニックの小禄雅人先生のご協力のもと、難病医療相談会(膠原病系疾患)を開催いたしました。参加された方から「専門の先生のお話を聞くことが出来て良かったです。完治することは出来なくても、寛解を維持することが大事だということが分かりました。」「薬の効果や副作用について詳しく聞くことが出来て良かったです。主治医の先生と今後の治療法について良く相談したいと思います。」といった声が聞かれました。
2024年度の難病医療相談会は今回が最後となります。2025年度も先生方のご協力をいただきながら開催していきたいと思っております。日程が決まり次第、アンビシャスホームページや会報誌でご案内する予定となっておりますので、参加ご希望の方はぜひご確認ください。
ご協力いただきました先生方にこの場を借りて感謝申し上げます。
アンビシャスメモ
保健所スケジュール
各保健所、2月の予定はございません。
【北部保健所】 Tel:0980-52-2704
【中部保健所】 Tel:098-938-9883
【南部保健所】 Tel:098-889-6945
【那覇市保健所】 Tel:098-853-7962
【宮古保健所】 Tel:0980-72-8447
【八重山保健所】 Tel:0980-82-3241
令和7年度【6月開講】障がい者委託訓練生募集
【募集期間:令和7年4月1日(火)~23日(水)】
【訓練期間:令和7年6月2日(月)~令和7年8月29日(金)】(3ヵ月間)
政府・沖縄県の令和7年度予算成立および沖縄県と訓練実施機関との契約をもって正式に開講が決定しますので、状況により開講しない場合があります。あらかじめご承知おきください。
浦添校管轄
コース名:繁殖養豚実務科(実践訓練)
定員:1名
管轄校:浦添校
募集対象:知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病
訓練場所:八重瀬町
委託先:株式会社那覇ミート 東風平農場
コース名:食肉加工実務科(実践訓練) b 定員:1名
管轄校:浦添校
募集対象:知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病
訓練場所:南城市
委託先:株式会社那覇ミート 大里工場
※受講料無料(但し保険料等は自己負担)
※衛生管理の観点から、施設内へ立ち入る際は当施設内でシャワー入浴が必須となります。
※詳しくは、浦添職業能力開発校へお問合せください。
【お問合せ先】TEL:098-879-2560
具志川校管轄
コース名:介護補助サービス科(実践)
定員:1名
管轄校:具志川校
募集対象:身体障害(上肢)、知的障害、精神障害、発達障害、その他(高次脳機能障害、難病)
訓練場所:宜野湾市
委託先:ふれあい介護センター(介護複合施設ふれあい 愛知の丘グループホームふれあい愛知)
コース名:リネン類クリーニング科(実践)
定員:1名
管轄校:具志川校
募集対象:知的障害、精神障害、発達障害、その他(高次脳機能障害、難病)
訓練場所:宜野湾市
委託先:沖縄綿久寝具株式会社(宜野湾本社工場)
※受講料無料(但し保険料等は自己負担)
※詳しくは、具志川職業能力開発校へお問合せください。
【お問合せ先】TEL:098-973-6680
こころの現場から
一歩踏み出せるか否か
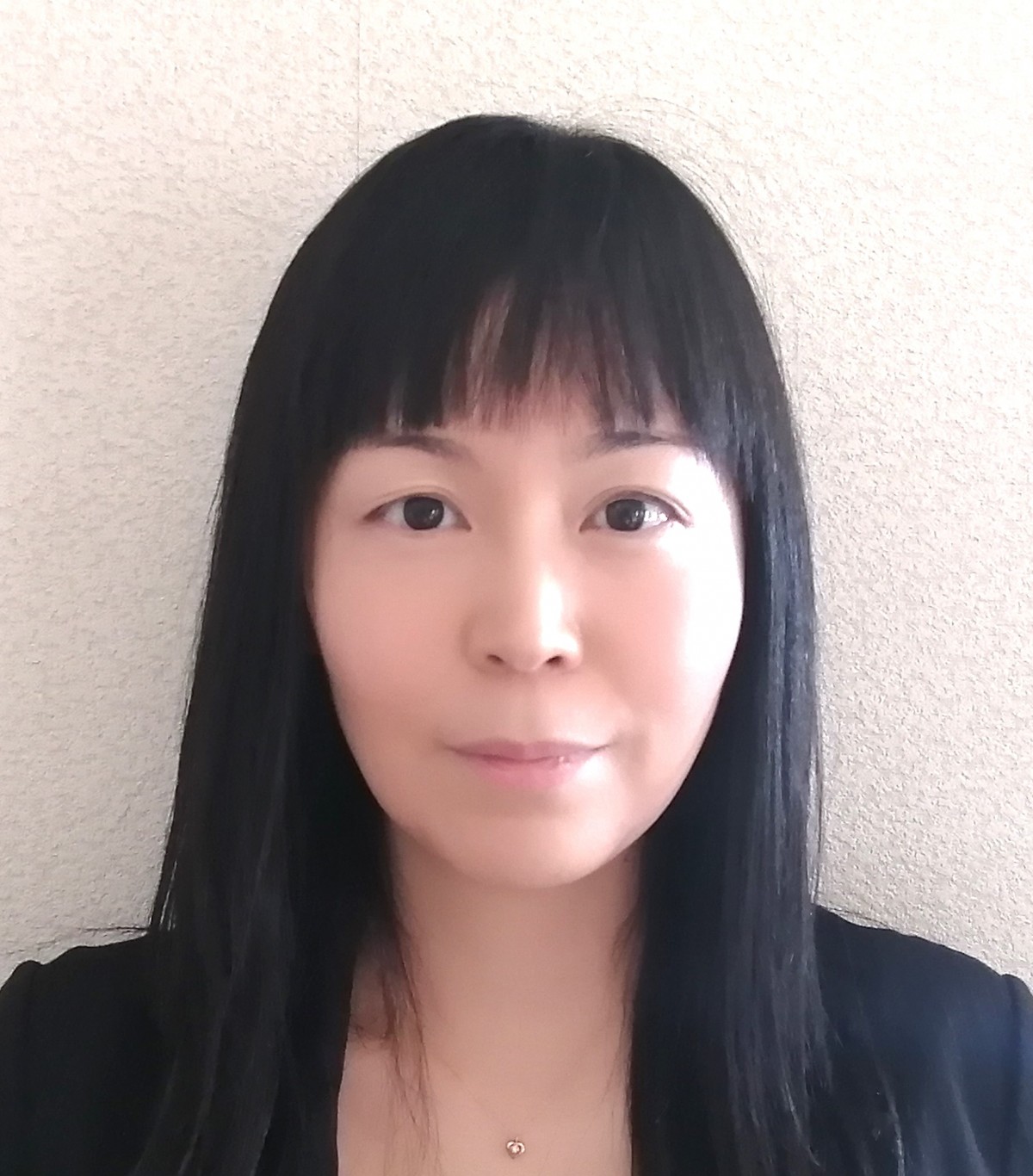
臨床心理士 鎌田 依里(かまだ えり)
相談の際に、一度相談しただけで自分の気持ちがまとまり「よしやってみます」と自分で一歩踏み出せる人もいれば、多くの人に同じ悩みを繰り返し相談しても次の段階に一歩も進めない人もいます。
まず、聴く側の態度として、相談をしてくる人の話を本当の意味で十分に傾聴できているとすれば、一度の相談でも「よしやってみます」と自分で一歩踏み出すような力を与えることができますが、聴く側が十分に聴かないまま良かれと思った助言をしてしまったりすると、相談をした人は十分に聴いてもらえていないので何度も同じ相談を繰り返して一歩も前に進めない状態になります。
次に、相談をする側の問題として、こころが健康である人が何か壁にぶち当たったときに相談をすると、一度相談をしただけでも次の一歩踏み出すことができます。しかし、元々、自尊心が低く、幼少期から「お前の選択がおかしい」と言われていたり、「お前なんかいらない子だった」「生まれてこなければよかった」等と言われて育ってきたり、学童期もしくは中学や高校で「自分なりに頑張ったことを応援してもらえた経験がほとんどない子」については、やはり大人になっても状況を変えるための一歩を踏み出すことが困難なようです。
自尊心が低く一歩踏み出せない状態が長く続くと、親身になって支援をしてくれていた人も諦めの気持ちが強くなってしまい〈どうせできないんだな、この人〉と思います。そう思われた結果、自尊心の低かった人は「やはり自分はダメなんだ」と再認識し悪循環に陥ります。
いろいろなものを抱えた人が相談には訪れます。相談者が一歩踏み出せるためにも丁寧な傾聴と諦めない気持ちが相談を受ける際に必要なのです。
つぶやきチャンプルー
患者のホンネとは

著:照喜名通
ある医師から、「患者さんの本音を聞くにはどうしたら良いでしょうか?」と尋ねられたことがあります。というのも明らかに処方された薬を飲んでいないと思われるが、患者本人はちゃんと飲んでいて残薬はないと言っているようです。もしかしたら本当に飲んでいるのかもしれないのですが、患者側にはそれなりの理由があるのかもしれません。
「飲んでいないと言うと医師に怒られるのかも」「良い患者と思われたい」「判っているが効いている感じはしない」「副作用が怖い」「どうせ医療費負担は変わらないから、病院に儲からせてあげる」などなどが想像されます。その患者それぞれに答えをもっていると思います。患者も医師も互いにゴールは“治る”“安定すること”ではあると思いますが互いに対話が必要です。処方された薬を飲まないで外来の際に更に処方されると、医師は検査結果などでその薬が効いていないのであれば、違うもっと強い薬を処方する判断になる可能性もあります。
また、医療費のほとんどは税金で賄っているので税金の無駄使いと言われてしまいかねません。患者の言うことをただ鵜呑みにしすぎる医師にも問題がありますし、外来の短い時間での患者と医師との関係性を構築することは難しいです。
患者側のヘルスリテラシーの向上の研修会などアンビシャスができることないか模索中であります。
シリーズ 「患者学」第120回
「〈いのち〉をケアする医療」について
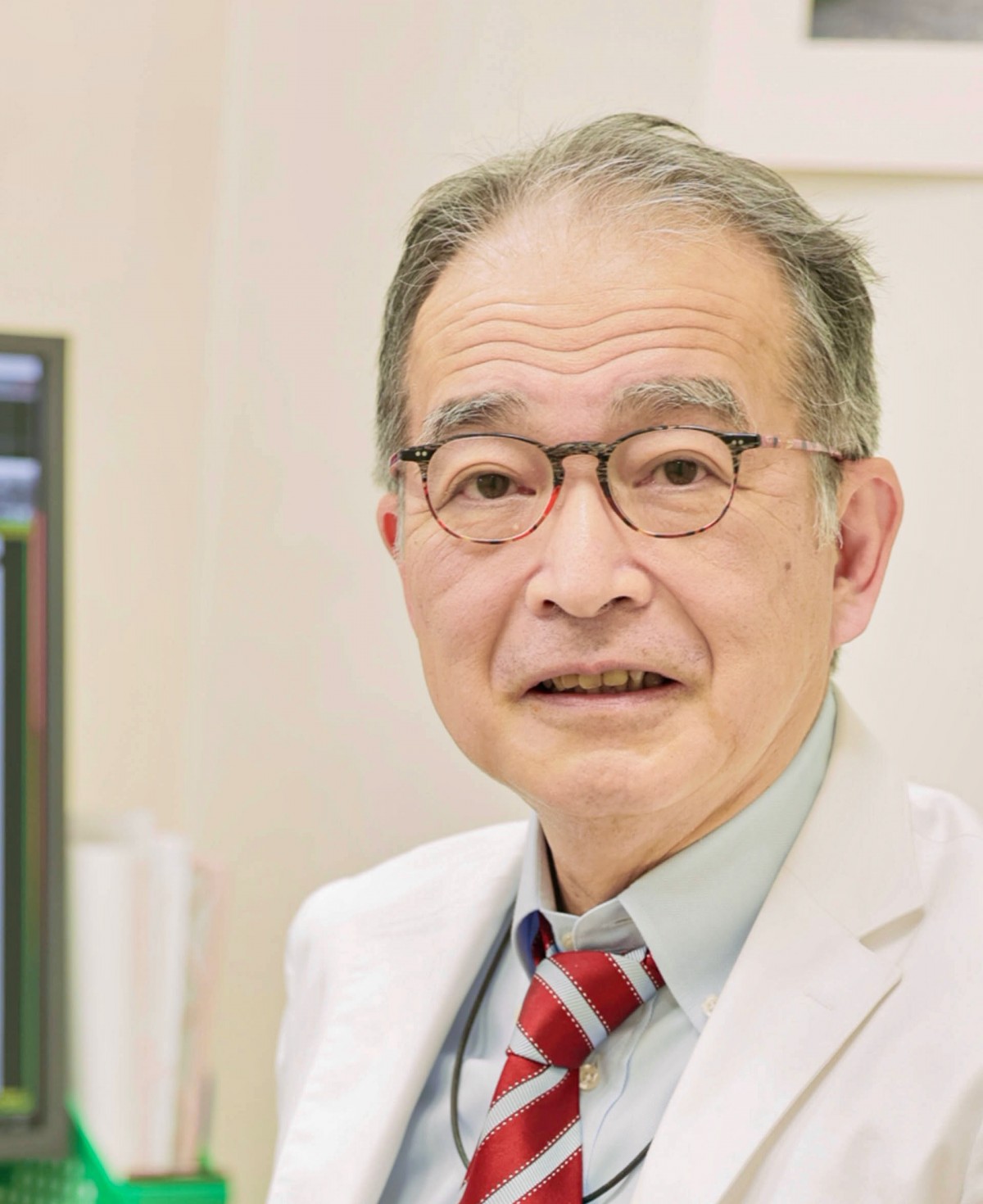
慶應義塾大学 名誉教授 加藤 眞三著
アンビシャス会報誌での連載
アンビシャス会報誌での連載も第120回を迎えました。毎月の刊行ですから、丁度丸十年を迎えたことになります。照喜名さんとのご縁により長期間にわたり連載をさせていただいたことを感謝しています。
「患者の力」(春秋社)を発刊したのが2014年であり、その時に沖縄での講演会をさせていただきました。その前に出版した「患者の生き方」(春秋社)が2004年であったため、できれば2024年に三冊目を出したいと、2021年頃より準備してきたのですが、この10年間の気づきを一冊の本にまとめるためには想像以上の時間が必要でした。ようやく、2025年4月に春秋社から出版できることになりました。
「〈いのち〉をケアする医療」の準備
新刊本の内容は、患者さんや一般市民向けであり、本誌に書き綴ってきたものをベースにしました。ただし、一冊の本として読んでもらうためには全体としての流れが必要であり、そのことで相当悩みました。さらに、2021年に大学を退職してから、OA高輪クリニックで一般診療をおこない、上智大学では傾聴人材養成講座で傾聴の演習などに関わることになり、それまでとは異なる視点で医療を見ることにもなりました。そのため、この本の後半では大学退職後の最近のわたしの関心事が大きな部分を占めています。
さて、本のタイトルは、当初の案は「ヒトへの医療から人間への医療へ」というものでした。ヒトとは、科学的にみた生物としての人を指しています。そして、人間とは、物質としての身体だけではなく、心理、社会、スピリチュアルな三つの次元をも含めた生物科学的だけでなく人文科学的側面も含んだ人を指します。つまり、人間を単なる動物として診るのではなく、魂をもち社会活動を行いながら感情に揺れ動く身体をもった人間として診る医療へ今後移行してもらいたいという願いを込めたものでした。
しかし、ヒトと人間の区別が分かりにくいという声を聞くなかで、それでは何を最も大切にしたいのかといえば、それは〈いのち〉ではないかということで「〈いのち〉をケアする医療」というタイトルにしました。
〈いのち〉とは
さて、この〈いのち〉が、また分かりにくいものと感じられるかも知れません。〈いのち〉は、英語でLifeとして表される言葉に相当する大和言葉です。漢字で表現する生命(せいめい)だけではないのです。そこには人生という意味も含まれています。そして「いのちの源」といえば超越する存在、すなわち神とかハイヤーパワーとか宇宙の意志とかが相当します。各個人には〈いのち〉の源から分け与えられた魂というものが存在します。それら全てをひっくるめて〈いのち〉と表現しました。
今後、AIとロボット技術が医療を大きく変えていくものと考えられます。その時に、患者さんはどのような医療を受けられるのか、医療をどのように変えていけばよいのか、医療者とどのように付き合えば良いのかなどを考えてもらえる内容になっていると思います。どうぞ、是非手に取ってお読みいただければと思います。回し読みでも結構ですから、一人でも多くの人に読んでいただきたいと考えています。
希望のある未来、希望のある社会、希望のある医療に向かって、一緒に進んでいこうではありませんか。
- 慶応義塾大学看護医療学部
名誉教授 加藤 眞三 - 慶應義塾大学名誉教授。上智大学グリーフケア研究所研究員。
患者と医療者の協働関係を作り上げることをテーマに公開講座「患者学」や著作 等を通じ、患者も自ら積極的に医療に参加する啓発活動に取り組む。
加藤先生の YouTube配信中です!
「Dr.シンゾウの市民のための健幸教室」
加藤先生の最新書籍:肝臓専門医が教える病気になる飲み方、ならない飲み方
出版社:ビジネス社
患者団体からのおたより
JRPS沖縄より 2月交流会の報告
毎年恒例のカラオケ交流会を、2月2日に那覇セントラルホテルで開催しました。当日は、北は名護から南は宮古まで会員や家族など総勢45名が参加し、食事を楽しみながらカラオケで盛り上がりました。普段なかなかお目にかかれない方々とも近況報告などおしゃべりできて、楽しいひと時を過ごしました。
2月16日には、沖縄視覚障害者福祉センターで「患者同士の交流会&iPhone勉強会&ロービジョンケア講習会」を開催しました。iPhone勉強会は、iPhoneを使ってみたいけど使えるかどうか心配という方や、iPhoneは持っているんだけれども操作がよく分からないといった方向けの勉強会です。今後も継続して勉強会を開催しますので、ご興味ある方は参加してください。
ロービジョンケア講習会は、福岡視力障害センターの山田信也先生を講師としてお招きし眼のリハビリについて学びました。自分の見え方を理解して保有視機能を活用トレーニングをすることで見え方が変わり生活が変わる。見えづらさで困っている多くの方に目のリハビリを実践して欲しいと強いメッセージをいただきました。
沖縄県網膜色素変性症協会
八重山クローン病・潰瘍性大腸炎患者 家族の集いより 交流会の報告
2月22日に八重山保健所にて〈八重山クローン病・潰瘍性大腸炎 患者 家族の集い〉の交流会を開催しました。
新型コロナ感染症の流行のため、これまで活動を自粛しておりました。令和6年11月に5年ぶりの交流会を開催し、5名の参加者がありました。その内2名は診断されて日が浅く、食事制限に不安があるようでした。経過が長い参加者から食事制限とどう向き合っているか、食事に気を付ける時期を伝え「安心できた。勉強になりました。」と感想をいただきました。
今年度2回目の開催となった2月には、4名の方が集まりました。大腸内視鏡検査の負担について共感し合いながら、検査をどう乗り越えているか話し合い、それぞれの対処方法があり興味深かったです。また、交流会を無理なく継続して開催する方法について話し合い、3ヶ月に1回の2月、5月、8月、11月の第4土曜日に開催してみることになりました。
今年度、2回患者会を行い、同じ疾患について語り合える場、共感してくれる人がいるというのは安心感につながります。参加に興味がある方、情報が知りたいという方はお気軽にご参加ください。
八重山クローン病・潰瘍性大腸炎 患者 家族の集い
代表 内間洋子・大濵 明美
今月のおくすり箱
この薬はいつまで使えますか?
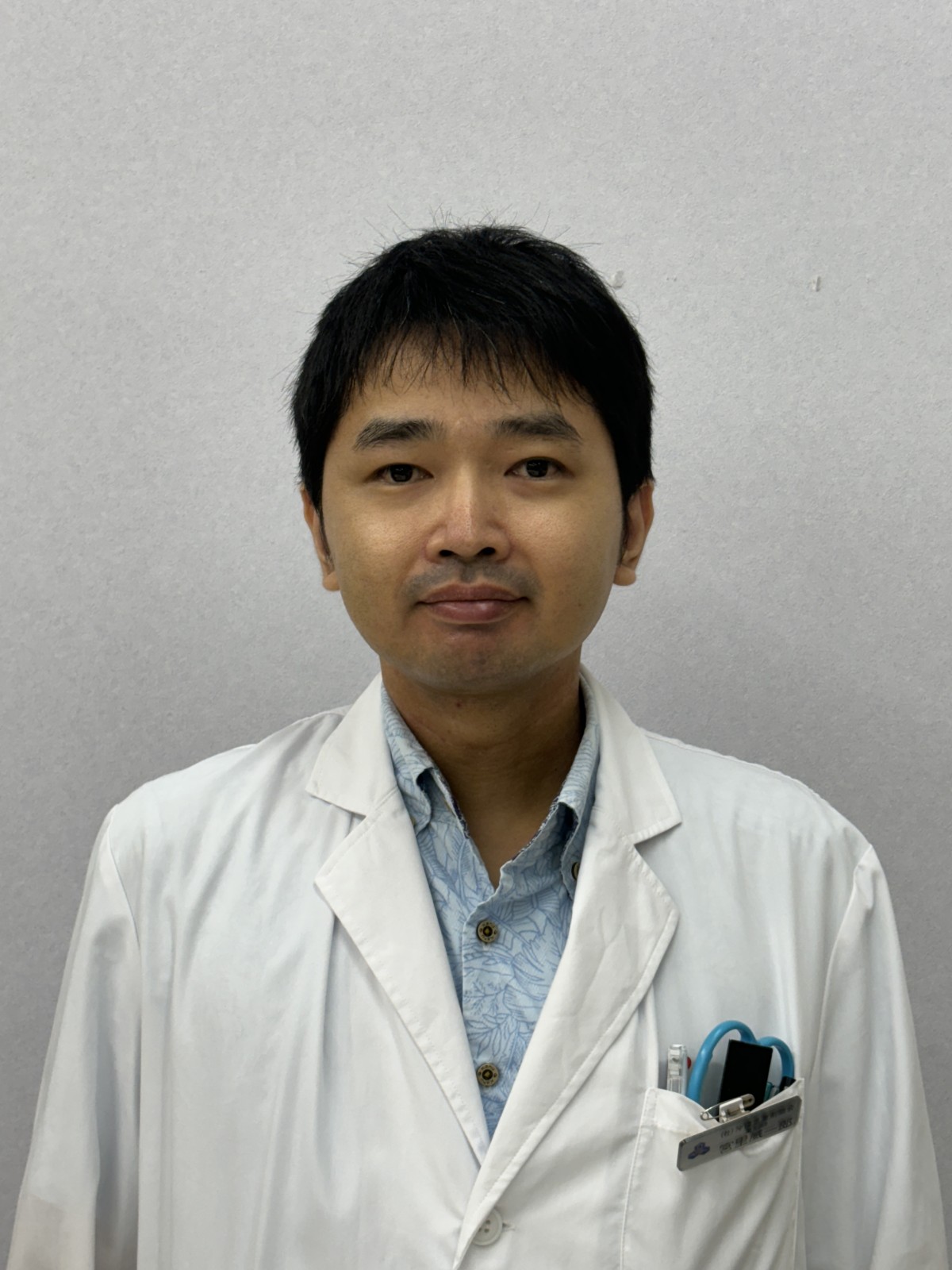
沖縄県薬剤師会 宮里 威一郎
「薬は食べ物じゃないから腐ったりとかしないでしょ?」と言われることがあります。薬は人工的に合成されたものなので、確かに食品のような腐り方をしていくことはありませんが…
私たちが使用する薬は、一般的に製造から2~3年を使用期限となっていることが多いです。その期限を過ぎていると、十分な効果が出なかったり、劣化した成分が体に悪かったり。
そこに、工場で製造されてから薬局に届くまでの期間、薬局で保管されていた期間を経て皆さんの手元に届けられます。薬局では定期的に期限チェックを行っており、品質の確保されたお薬をお渡しできるようにしています。
病院や薬局から出るお薬は患者さんのその時の症状に合わせて医師が処方したものです。別の機会に同じ症状が出ても、同じ診断とは限りませんし、使用期限がどの程度残っているかも不透明です。そういった場合には残っていた薬をすぐ使うのではなく、まず医師・薬剤師に確認を取るようにしてみてください。
アンビシャス広場
~エッセイ~ 「ファインチャットはPCじゃ…」 渡口 正さん(ALS)
令和5年8月、服用タイプのラジカットを処方してもらえるようになったことから、私は、本格的な在宅療養生活へ移行し、主治医も豊見城中央病院の久田先生に代わったが、その前後から私にはとても気になってることがありました。
それは病院スタッフ、訪問看護師、ヘルパーとの意思疎通がスムーズに図れないという課題です。つまり、病院スタッフの皆さんらは、アナログの文字盤を使って我々の意思を確認することはなく、一方的に質問するから当然我々の意思は伝わらない。
幸い私は、NPO法人アンビシャスの照喜名さんらのお陰で、コミュニケーションツールの「miyasuku」、「伝の心」、「ファイン・チャット」を実際に使ったり、それぞれの機能や性能を確認することができました。
私が言えることは、パソコン(PC)の苦手な人でもファイン・チャットはお勧めです。なぜならファイン・チャットはPCじゃないから~ッ!?ぼーと生きてたら、チコちゃんに叱られるッ!ってか? 照喜名さんは、我々難病患者のとても頼りになる味方です。
※このコーナーの寄稿者(故)渡口正様より生前にお預かりした原稿は、ご本人の意向により最後まで掲載いたします。
お勧め映画/DVD情報
ハリソン・フォードのオススメ作品
1)スター・ウォーズ シリーズ
1977年から2023年で旧3部作と新3部作と続3部作の9作品。
2)インディ・ジョーンズ シリーズ
1981年から2023年までに、全5作品。
3)ブレードランナー シリーズ
1982年と35年ぶりの続編2017年『ブレードランナー 2049』はアカデミー賞で5部門にノミネート2部門でを受賞。
4)心の旅 1991年
仕事一筋で家庭を顧みない弁護士が事故で記憶喪失になり家庭の問題やリハビリする中、どう変わって行くのか。
5)小さな命が呼ぶとき 2010年
アカデミー賞長編アニメ映画賞、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネートされた。映画の舞台は横浜市で、兄と妹の話。
★渡久地 優子{進行性骨化性線維異形成症(FOP)}★
今月の占い
- 牡羊座 3/21-4/19
身の周りを整理整頓して
☆リフレッシュ法:掃除 - 牡牛座 4/20-5/20
リラックス出来る時間を
☆リフレッシュ法:スキンケア - 双子座 5/21-6/21
友人や家族と楽しい時間を
☆リフレッシュ法:飲食 - 蟹座 6/22-7/22
笑って脳のストレスケア
☆リフレッシュ法:ネット観覧 - 獅子座 7/23-8/22
疲れる前に休息しよう
☆リフレッシュ法:歌唱 - 乙女座 8/23-9/22
趣味で充実した時間を
☆リフレッシュ法:読書 - 天秤座 9/23-10/23
美味しい物で栄養補給
☆リフレッシュ法:DVD・TV鑑賞 - 蠍座 10/24-11/21
挨拶は笑顔を忘れずに
☆リフレッシュ法:音楽鑑賞 - 射手座 11/22-12/21
振り回されず自分らしく
☆リフレッシュ法:散歩 - 山羊座 12/22-1/19
お洒落を冒険してみて
☆リフレッシュ法:お風呂 - 水瓶座 1/20-2/18
ストレスとアウトプット
☆リフレッシュ法:談笑 - 魚座 2/19-3/20
早寝早起きで健康的に
☆リフレッシュ法:ドライブ
編集後記
今月の「表紙は語る」にご寄稿いただいたのは、小渡里子さんの体験談です。アルビノ(眼皮膚白皮症)という難病を患い生まれ、様々な壁を乗り越えながら新しい目標を立て、自分ができることをしようと前向きな気持ちが伝わり、読む側は勇気が芽生えます。子供の頃は「うーまくー」であったとのこと。その、うーまくー精神でコンサートに出演したり、新たな活動へと進む様子がうかがえます。小渡さんの体験談は2か月にわたって掲載します。さて、次号の会報誌お届けするのが楽しみになってきました。
4月は新年度の始まりです。沖縄は初夏を思わせる季節ではあるのですが、桜満開の中での新入学・新就職を迎えられる地域が羨ましく思います。我が家での衣替えはGWです。保健所などの行政では人事異動で新たな保健師さんなどと新たな一歩になるので、ご挨拶から連携の始まりです。患者会の活動も少しづつ再開してくるようです。患者会の毎月の活動についての把握は各月の会報誌をご活用ください。公式LINEも毎月発行しています。公式LINEでしたら、WEB版もいつでもどこでも会報誌にアクセスできます。
文 照喜名 通
Copyright©2002 NPO Corporation Ambitious. All Rights Reserved.